メニューが表示されていない場合は、ブラウザのJavaScriptをオンにする必要があります。
それでもメニューが表示されない場合は、下のフレームボタンでフレームメニューでご覧下さい。
|
メニューが表示されていない場合は、ブラウザのJavaScriptをオンにする必要があります。
それでもメニューが表示されない場合は、下のフレームボタンでフレームメニューでご覧下さい。
|
|
小説ってほどじゃなく、雑文だけど
なぜか、1986年に1976年、21才の頃の事を書きたくてペンを握った。 学生の頃、俺は深川辰巳って名前でライブをやっていた。 全て事実という訳でもなく、全てが嘘という訳でもなく書いた。 でも紛れもない俺の青春時代の話。 ゆったりした時にゆっくり読んでくれたら嬉しいな。 TOMMY F KING 想い出‘76 弦を張る時には、いつも独特の緊張感を覚える。 俺は今夜のコンサートで起こり得るだろう場面をスライド写真のように次々と想い浮かべながら、ギターの弦を張り替えていた。 メーカーにもよるが、俺はほどよく柔らかなゴールド弦を好んで使用していた。張ってジャラジャラと掻き鳴らしたり、チューニングしたりを繰り返していると、やがてサウンドホールに乾いた幅のある最も好みの音を見つけ出すことができた。しかし、その状態は、半日間も持続出来ればよい方で、俺はいつも演奏時に最高の音が出せるように、この作業には、細心の注意を払っていた。 風は強く、古びたアパートの窓枠がガタガタと悲鳴を上げている。俺は、再度に渡るチューニングを終えると、丹念にギターのボディを拭きあげ、飲み干したビールの空缶を握り潰し、錆びたストーブの前で身繕いをした。 外へ出ると、すぐ南側に海が見え、やがて砂浜と松林が視界いっぱいに拡がっていく。俺は、アパートを出る時、無意識のうちに水平線に眼を向けている。俺は、特に夕暮れ時のこの町の風景が気に入っていた。大学に通うには、かなりの距離があったが、ここの風景達が好きなことで、不便さは、そう気にはしていなかった。 電車は、夕日に向かって無気力に走り、その紅く染まって走る電車の姿は、まるでもう話すことの無くなった一人ぼっちの老人に見えた。 この時間、この街の商店街では通り一面に行商達の威勢のいい売り声が響き、その声にこだまするように主婦達の掛け合いが続く。 そんなやり取りを聞きながら、俺はあてもなく、よくこの商店街をぶらついてみたりする。さほどべとつかないこの街の色に染まっていると妙に心が落ち着いてきて、この街の優しさを実感として味わうことが出来た。 コンサートは、市の繁華街からすこし外れた港の見えるビルの一室を借りて開かれる。 「スピリッツ」というアマチュアの企画グループが定期的に行っているコンサートで主に十人位の学生や社会人達がこのスピリッツを中心に地道なコンサート活動を続けていた。その殆どがフォークギター一本による演奏スタイルで自作の曲を中心にコンサートを続けていた。 聴きに来る客も大半が同年輩の顔馴染みで、多い時で二百人、少ない時で五十人位がこのスピリッツのコンサートに足を運んでくれていた。 この種の企画グループは、この街にも数多く有ったがスピリッツは、演奏内容を任せてくれるので、俺も、もう二年位、約三ヶ月に一度の割で出演させて貰っていた。 会場近くの喫茶店に着き窓越しに中を見たが客は無い。それでも構わず、俺はギターを押し込むように中へ入り、ビールを注文すると、まずコップ一杯一気に腹まで流し込んだ。 二杯目を口にしている時、ドタドタと二人の客が店に入って来た。 「ごめん、ごめん、遅くなって。この辺りは、解りにくい所だね。」一人が長い髪を右手で掻き分けながらギターケースを空いた席に無造作に投げると、俺の前に腰を降ろした。もう一人もニヤニヤと笑いながらドラムスティックをテーブルの上に乗せ椅子についた。 俺は、それまで一年半位一人で演っていたが、自分の音楽そのものにもっとパワーを求めていたし、そのパワーを吸収することで新しいスタイルを見つけることが出きるのではないかとバンド結成を考えていた頃で、三ヶ月程前に手頃な練習スタジオを見つけだし、大学で知り合ったこの男達とアメリカンスタイルのフォーク&ロックバンドを組み練習を重ねてきた。曲は、全て、それまでに俺自身が書いたものでアレンジも練習中に俺の指示で行ってきた。毎日のように練習してどうにか十曲ほど仕上ったので今回俺の方からスピリッツに出演を依頼し、今夜そのコンサートが実現することとなったのだった。 昨日も十二時頃まで練習をしていて、二人共慌てて出てきたらしく顔には、うっすらと無精髭が見えた。 「いやぁ、俺も今来たばかりさ。まだ眠くってね。」俺は、二人に合わせるように答え、ビールを注いだ。リハーサルまでまだ少しあったのでそれから三十分程の間、取り留めもない話や打ち合わせで時間を過ごした。 ベース担当の広兼とは、大学の同じゼミで知り合った。胸までもある髪と一年中着ているエンジ色のジャンパーが印象的な人あたりのよい男だった。ドラムの飯田は、広兼が紹介してくれた男でやはり同じ大学で、スタジオミュージシャンを目指しているという、それなりのテクニックを持った背の高い男だった。 会場の入口付近には、既にスピリッツのスタッフが受付けを出したりポスターを貼ったり忙しく動いていた。入口を抜けると部屋の中には、照明だけがセットしてあり、アンプやマイクが無造作に置かれた床には、コード類がいく重にも重なって散乱し、ちょうど五、六人のスタッフがステージのセットに取りかかっているところだった。 やたらと天井の高い全面白壁のホールだった。 どんどんステージの方へ歩み寄っていくといきなり後の方からスピリッツのリーダーの山脇さんが声を掛けてきた。 「やあ、リハは、後二十分位してスタートね。どう?ここ、割といいホールだろ。」 「はあ。」俺は、暗い客席に一人座っている山脇さんに驚いて振り返り、それからホール全体をゆっくり見回した。 「かなりよさそうなPAですね。ここだとあまり大きい音だと割れそうなので全体的に絞ってミキシングをお願いします。」俺はステージに登り中央にセットされたばかりのマイクを通して言った。山脇さんは、笑いながら「OK、OK。」と手を振った。 飯田が、落ち着かずドラムのリムをコツコツ叩き始めた。そして確かめるようにバスを踏みスネアーをロールする。かなり堅い音がして、狭いホールの隅々まではじけ飛んだ。広兼のチューニングが済むのもまどろっこしい思いで、いきなり二曲演奏した。 俺の口から飛び出した声は、しゃがれていて、まるでカーネギーホールで歌うBOB DYLANのような気分だった。「ミキサーさん、どうですか?もうすこし、モニターが拾ってくれると、もっと演りやすいんですけど…。」 俺は、客席に居るはずのスタッフに声をかけた。「はい、オーライです。モニターは、それで精一杯なんです。頑張って下さい。」暗がりの方から声がかえってきた。 俺達と入れ代わりで今夜出演するもうひとつのブルースバンドがリハーサルに立った。メンバーは、やたらと汚らしい風体で、ブルースハープのフェイクした甲高い音でマイクがキンキンと鳴いていた。 俺達は、近くの飯屋で取りあえず腹ごしらえした。会場に戻ると場内には、もう百人程客が集まり、受付にも数人の男女が立話して、開演を待っていた。 楽屋もないホールの隅で俺は、深呼吸し、それからスタッフに合図を送り、二人のメンバーの肩を軽く叩くと無言でステージに上った。ギターのストラップを掛け、チューニングするといきなりカウントを足で取った。緊張感は、ステージの二人へ響き、交差して客席へと飛び散った。イントロすら待てない気分で俺は歌い出した。スポットが俺を追いかけてきたが、俺は、天井に眼を据えたまま、肩でリズムを取り歌った。歌い出したとたん、歌いたい事が頭の中を占領してしまい、もうメロディのことなんて気にならなくなる。3コードに乗せ俺は、カードのように言葉をばらまいて見せた。 歌うことにエネルギーを集中して、歌っている以外は、もう口を開きたくなくなっていた。 「とりあえず」
作詞 田中善久
作曲 深川辰巳
あわただしそうに 時間だけが過ぎていって
ちっともはかどってなくて義理と借金
喉をからして 話したところで 方法論には 至らない
飲んで飲まれて 飲まれて飲んで
風は吹くもの 吹かれるもので 信じるってことは たったひとつの 言葉じゃないよ
僕は 毎日のように 人と会っては 酒をくらっています
明日じゃ遅いことって いっぱい有りますよね
東京から京都 寂しくなんかないだろう 神戸から博多 悲しくなんかないだろう
とりあえず ちっぽけな自由 雨上がりの空模様に 一服二服 夜の波にグラス傾け
※飲んで飲まれて 飲まれて飲んで
額から汗が落ちてゆく。ポマードで撫で付けた髪も汗で流れてきた。黒い皮ジャンが暑かった。俺は、四曲たて続けに演奏すると一息ついて、Gパンの尻で手の汗を拭いた。
割におとなしい客層だったが反応はまあまあで、俺の没頭度に半ば興きながらも、奇妙な緊張感が、俺達と客の間に出来上がっていた。
一度、ステージに上がると、もう俺は客のことが気にならなくなる。とにかく大切なことは、自分がいかに燃焼しつくすかということだ。
俺は、歌をうたう時だけが、正直な自分で居れる時だと感じていた。ステージに立つということは、俺にとって、人に裸を見せているようなもので、俺は自分の内側にあるエネルギーを使い果たすことで自分を取り巻くしがらみから解放される気持ちになる事ができた。
バンドメンバーの紹介をしてまた、四曲続けた。今夜は、特にベースのリズムが生きていた。俺は、時々、広兼の方を見てウィンクして見せた。
「夜明け前」
作詞・作曲 深川辰巳
珈琲カップの中に顔がある 肉体は すでに僕の手の届かない所さ
やりたいこともなかったが やらなきゃならないこともなかった
明日という奴がちょうど 僕の鼻先までやって来ていた
君にはいた言葉の重みが 僕の頭を鉛にしていた
腹ばい夜明が僕の肩を なめた時もう僕には
君の迷路パズルを解く 根気なんて失くしてしまっていた
どこにでも転がったよくある話さ 僕が口を開いたとたん君は
地球の裏側に放り出されていた 痛みも悲しみもなくて
ただやるせなさだけが舌の上で 音を立ててはい廻っていた
早く出ていっておくれ 僕は もう新しいマッチをすってしまった
夜が明けたら君と僕を 関係付けるものなんてない
もう泣くのを止めるんだ 僕の足は 床を踏み始めている。
照明が眼の中で弾け出した。音は、毛穴から吸収されて、脳まで行きつくとフィードバックして俺の体中から吹き出した。口は乾き頭の中は、カラッポになった。
将来のことなんて考えていなかった。この先自分がどうなるのか、ましてや自分をコントロールするなんてできる筈もない。足踏みをして、肩を揺って俺は、歌った。とにかく今は、歌うことに集中していたかった。演奏の評価や出来はともかく、今の自分をステージの冷たい床の上に投げ出したかった。
気が付くと、予定の曲を全曲演り終えていた。「ありがとう。」と口にしたけどマイクには、入らなかったかもしれない。
スポットが消えた。俺達が降りてゆく階段まで拍手が追って来た。疲労感の中に少しだけ満足を味わっていた。でも、もう俺は、もぬけの殻で客席の方を見る力もなくなっていた。
たいてい、演奏が終わるとメンバーでその日の出来について、あれこれ言い合いをする筈なのに今夜は、飯田も広兼もかなり疲れた様子で口を開こうとはしなかった。コンサートを聞きにきてくれた数人の知り合いと一言二言挨拶を交わすと外へ出た。
外は、もうすっかり暗くなっていて、汗をかいた背中に風が冷たかった。俺は、Gパンのポケットに両手を突っこんだまま会場の前を流れる川にかかった橋の欄干にもたれ、ホールから遠く聞こえてくる俺達の後に出た連中のブルースに耳を傾けた。
掻き鳴らすギターの低音部がなんだか、ドンドンと足踏みのように聞こえ、けだるいハーモニカの音は、人の歓声のように宙に舞っていた。「なんだか今夜は、熱っぽいので先に帰るとするよ。」飯田は、ドラムステックを尻ポケットに差しながら広兼と俺を見比べるように言った。「だって今夜は、この後、企画の人達と打ち上げがあるんだよ。すぐ近くのパブで。それに出てから一緒に帰ろうよ。」広兼がなだめるように言った。
実を言うと俺ももう帰りたかったのだが、つい、広兼に合わせて飯田を引きとめた。「そうだよ。ちょいと飲んで一緒に帰ろう。どうせ帰ってももう寝るだけじゃない。」
さっきまでの落ち着かない雰囲気が嘘のように、ホールは静まりかえっていた。すでに客も帰った後で俺達は、機材を車に積み込みホールを出た。スタッフと俺達は、ネオン街を通り抜け町のはずれにある「サッチモ」という飲み屋にはいった。
「深川君が歌いながら動くんで声を拾うのに苦労したよ。」山脇さんが席につくなり俺に自分で作ってくれたバーボンのロックを差し出しニコニコと話しかけてきた。「おかげで今夜は、思い切りやれました。嬉しかったです。有り難うございました。」広兼も飯田も一緒に頭を下げた。
企画のスタッフ連もそしてブルースバンドも、みんなよく飲んで、よく騒いだ。だんだんと酒も回り、音楽や女の事で議論に花が咲いていた。俺は、バーボンが効いて無口になってしまっていた。安っぽい酒が内臓にだけ火を点し、手足はやたらと冷たかった。店内いっぱいにJAZZが響き、笑い声があちこちで起こり、その内、店主までがテーブルを囲みどんちゃん騒ぎとなってしまった。
コンサートの後の馬鹿騒ぎは、恒例のことで、いつも最後には、肩を組んで、踊り出すのが常だったが、俺は、今夜、なんとなく馴染めなくて、広兼と飯田に目配せをして、店を出た。
酔って定まらない目を、街のネオンに向けながら、だまって後を歩く二人に振り向きもせず、俺は話しかけた。「このところ練習ずくめだったから、しばらく休もうか。」
二人と別れ、アパートに着いたのは、十二時を回ろうかとしている頃だった。ドアの内側から明りが漏れ聞き慣れたレコードがかかっていた。ドアを開けると、山口照美が壁にもたれ珈琲を飲んでいた。「なんだ、来ていたのか。」俺は、ギターから先に部屋へ押しはいるとそのままベッドに腰を降ろした。
内心俺は、一人になりたかったので勝手に人の部屋に上り込んでいた照美を見ても笑顔を繕うことができなかった。そんな俺の気持ちを察したように照美は、上眼使いに愛そ笑いを俺に向けた。「酔っているみたいね。珈琲を入れるわ。」照美は、大学で同じクラスの女の娘でビートルズの好きな育ちのいい女だった。よく哲学書なんかを読んでいて、それらしい理論を持っていたが、俺にしてみれば、それだけのことで、なんとなく心を開いて話し合える女としては、見てはいなかった。照美は、手持ちぶさたに、胸まで伸びた髪をいじりながらレコードに合わせて、少しハミングした。
「この頃、大学にちっとも出てこないのね。」「ああ、ずっとバイトしてたんだ。」俺はベッドに仰向けになり答えた。
「まる一日肉体労働でこき使われて、たったの四千円ポッキリ。ひどいもんさ。」「ゼミの先生が心配してたわよ。」
「すまないがレコードを止めてくれないか。今日はコンサートをやったんで、まだ耳の中がガンガンしてるんだ。」
「あら、そうだったの。声さえ掛けてくれれば、聴きに行けたのに…。」照美は、残念そうに呟き、ステレオのスイッチをひねった。
思い切り吐き出したタバコの煙りが風の止まったこの部屋でぼんやりとライトに照らされて、天井まで立ち昇ってゆく。「済まないが明かりを小さくしてくれよ。眩しいんだ。」
「なんだか、あやまってばかりね。私の方が勝手にお邪魔してるのに…迷惑してるんでしょ。」俺は、答えずタバコを揉み消すと眼を閉じた。部屋が暗くなり、照美も黙ってしまった。本棚に置いた目覚まし時計が、なぜか不規則な調子でコチコチ音を立てていた。
考えなければいけない事は、眼の前に山積みされているのだが、俺は、そいつを片っぱしから記憶の隅に放り投げ、一切何も考えないように、自分の思考回路のスイッチを切った。大学のこと。就職のこと。女のこと。そして音楽のこと。どれもこれも忘れ俺は、暗い部屋で、眼を閉じていた。「本当に迷惑だったら、帰るけど。」照美が、覗き込むように言った。俺は、また答えなかった。
沈黙に顔をゆがめながら照美は、そのまま俺の上に身を預けてきた。ぎこちなく、倒れ込み、俺の肩にしがみついた。慣れない化粧の香りに俺はムッとして、まつわりついて来た照美の髪を静かに払いのけた。「この頃ちっとも声をかけてくれないのね。」顔を上げた照美は、泣いていた。「大学でも会えないし、電話もくれないし…。」「実は、今、俺は、病気なんだ。学術的病名は、解らないけど、確かに今、病気で誰とも口をきく気になれないんだ。」「私、この頃よくボブディランを聞くのよ。特に、セカンドアルバムを毎日のように聞いているの。」
「俺は、もうディランなんて聞いてないよ。第一レコードをもう二ヶ月もかけてないんだ。」
「キスして。」俺の曖昧な返事を封じるように照美は、顔をこわばらせて言った。俺は、照美の髪を両手でゆっくりかき分け唇を重ねた。アルコールの勢か感覚がにぶっていて肩を抱いてみてもかえって無感情になって心が醒めてゆくのが判った。
「悪いけど、もう帰ってくれ。くたびれたんだ。」照美は、何も言わずに立ち上がり背中を向け髪をなおした。「貴方はただのいい人なのね。そんなに済まなそうな顔をすることは、ないわ。」そう言って振り返り無理に笑って見せた。
照美が部屋を出てゆくのを見送りもせず、俺はそのまま眠りに就いた。
通りを歩く女学生達の笑い声で目が覚めた。時計は、午後四時を指していた。ずい分と眠り込んだものだ。部屋全体が、オレンジ色のカーテン越しに差し込む日の光で紅く染っていた。俺は、目を開けたまま、しばらくの間ベッドにじっとしていたが、頭を左右に振って力まかせに起き上がりカーテンごと窓を開け放った。学校帰りの高校生が自転車を止め、立ち話をしていた。買物かごを手にした近所の主婦達の姿も見えた。風は、ひんやりと冷たく部屋の中の暖かい空気は押し出されるように部屋の外へ飛び出していった。
この頃俺は、眠っている時間が多かった。夜眠れなくて、やっと明け方に眠りこみ夕方ようやく目が覚めてもベッドから起きあがることができず、そのまま次の日までも、ただじっと目を閉じて過ごしてしまう日もあった。人が、このアパートにやってこないと部屋に閉じこもったまま、三日も四日も、口を聞かないことがあった。大学には、もう、一月行っていないし、大学の友人達と会うことは無かった。
俺は、一体、毎日何をしているのだろう。大学へ、何がしかの目的を持って来た訳では、ないし、ただ、それまでの親元での淡々とした生活に飽き飽きして、しびれを切らした頃だったし、ともかく、もっと自由で、ゆっくり考える時間が欲しいだけで、受験し、この街へ住みついただけの学生なのだ。
意味のない日々を二年間も送り、書き損じのレポート用紙のように、ポンとチリ箱に自分の人生を捨てているようで、募った恐怖が、やがて絶望感に変わっていくのを感じていた。ただひとつ、俺の本当の気持ちを表せるつもりの音楽にしても、ここ一年ほど全く新しい曲は、書けていない。もう、ぶつけるべきことが無くなってしまっていた。本当のところステージで燃焼出来るだけの魂をもう俺の中に見つけだすことは、できないようになってしまっているのではないかという不安がよぎる。頭と身体を切り放された自分にあせり俺は、イライラして手の平に汗をにじませた。
むしゃくしゃするので街でもブラブラしようと皮ジャンを背負っていると電話が鳴った。俺は、すぐ、照美の声を直感して受話器を取ったのだが、全くの知らない声で「RKBの者ですが、今井ディレクターからの託けで今夜七時に第二スタジオにバンドの皆さんでお越し願いたいとのことです。あ、それから、楽器もお持ち下さいということでした。」とてもスピーディーな事務的な若い男の声で、必要な伝言だけ云い終えると俺の曖昧な返事が終わらない内に一方的に電話を切ってしまった。
受話器を置いても、最初は、なんのことだか訳が解らなかったが、そういえば、昨日のコンサートで演奏が終わりステージを降りた時、気軽に話しかけてきたサラリーマン風の中年がいて放送局のディレクターだと名乗っていたのを思いだした。その時は、俺もステージ直後で興奮していて電話番号だけを教えて別れたのを思い出した。
なんとか、飯田、広兼共連絡がとれ俺達は、飯田の車に楽器を積み込みアパートを出て、中心街にあるRKBに飛ばした。
飯田が、興奮した声で「何だろうね。昨日の演奏が気に入って貰えたのかな。オイ、ひょっとしたら、レコードが出せるんじゃない?」と勝手に想像して笑いながらハンドルを切った。広兼にしても、「まだ飯も食ってないんだ。」と口をとがらせながらも、知りもしない放送局のディレクターに呼ばれたことに気をよくして、しきりに長い髪を撫でつけた。俺は、二人のどちらにも答えなかったけど、同じようにこれから起こるだろうことを勝手に色々と想像していた。
RKBに着くと、もう正面玄関は、閉めてあり、俺達は、裏へまわり守衛が指さして教えてくれた第二スタジオへと向かった。冷たい廊下を左に曲がると第二スタジオがあり、二重扉を押すとそこには、一流メーカーのアンプや機材が並べてあった。
「やあ、よく来たね。」リバーブの利いた声が天井のスピーカーから飛び込んできた。部屋の向こう側がミキサー室になっているらしく、ガラス張りの勢か室内灯が反射してよく見えなかったが、今井ディレクターらしき人が手を振ったのが判った。「今、スタジオが空いたところなんだ。録音の準備してるから、ちょっとそこでチューニングしながら待っていて。」
訳がわからず、立ったまんまの俺達に今井ディレクターは、例の調子で気軽に声を掛けてきた。五分も待っただろうか、今井ディレクターは、俺達のいる録音室の方へ降りてきてマイクまでセットしてくれた。「それじゃ、とりあえず二曲録音します。えーと、ほら昨日最初に演った曲とその次の奴。上からキュー出したら初めて下さい。」
放送局関係の人って殆どが、そのイメージ通りのタイプで一方的にどんどん話を進めていく。俺達は、今井ディレクターの持っているリズムにひっぱられてセットした。
俺は、堅い床を確かめるように足でカウントした。一曲歌い終わっても、OKが出ず、結局二曲それぞれにテイク4まで演らされて、録音し終わるまでに一時間もかかってしまった。気分的にとてもノルことなんかできなくてスタジオ録音自体初めてで、なんだか関係のないことばかり演奏中に思っていた。二人も萎縮してか、録音中全く口をきく余裕がなくて、時折、顔を見合わせては、互いにニガ笑いした。
「出来は、どう?」こっちの方が聞きたい位だと心で思ったが「いやあ、モニターがないんでよく声が聞きとれなくて…メロメロでした。」と答えた。「録音そのものは、いいと思うけど、さあ、こっちに上がってきて下さい。」今井ディレクターに呼ばれるまま、俺達は、ミキサー室へあがった。やたらとチャンネル数の多いP・Aとでかいデッキが目にはいった。
「よく来たね。まあ、そこに掛けて、楽にして下さい。実は、昨日偶然、君達のステージを見てね。ちょいと面白いんで録音させてもらったんだ。まだまだ荒っぽいけど、どこか感じれるものが有ると思うんだ。それで、今度、うちの主催でアマチュアバンドのコンテストをやるんだけど…ちょいと手直しすれば、かなりいい線いけると思ってさ。なにせ、僕もコンテストの審査員だし、優勝すれば、レコード会社と契約できるチャンスもあるんだよ。」
「そうなんですか。」突然の話で俺は、曖昧な返事をした。俺は、俺の書いた曲がレコードになるなんて夢にも思わなかったし、とても信じられなかった。それにこれまで人のために歌ってきた訳じゃないし、今井ディレクターの言葉に単純に喜びはしたものの、自分のこととして受けとめることは、できなかった。
「とにかくテープを聴いてみて下さい。」放送局なのだから、当然のことでは、あるが、自分の声とは思えないくらい、自分の演奏とは思えないくらい最高の録音状態だった。「いつからこのメンバーで演ってるの?」「ハァ、まだ3ヶ月位です。一緒にやりだしてから。」「いつもどこで演奏してるの?」「アマチュア企画のコンサートばっかりです。」
俺は、子供のように聞かれたことに答えた。飯田も広兼もただ、頷くばかり。「ああ、ほら、ここのメロディ、ちょっとフラットしてるでしょ。それから、サビのリズムが、ちょっと重すぎるよ。」「ハァ。」
曲のことになったら、細い部分をどんどん指摘された。「ここんところは、もっと解りやすい詞にしなきゃあ、なにが言いたいのかボケてしまう。もっとメージャーな曲作りを考えなきゃ。」
守衛の立つ、裏口に出た時は、もう九時を過ぎていた。寒さと興奮のため、肩がガタガタと震え、俺は、思わず自分の体を両手で抱きしめた。飯田が駐車場から車を出してくるまでの間そうしていると、やっとすこし落ち着いてきた。車は、音をきしませて止まった。俺と広兼が、車に乗り込むなり、バックミラー越しに飯田は、低い声で言った。
「なぜ、あんな言い方したんだ。俺は、深川もプロ志向だと思ってたよ。いや、そうじゃないにしても、こんなチャンスを蹴るなんて……。」駐車したままの車のウィンカーが無愛想にカチカチ鳴っていた。飯田は、今井ディレクターの好意的アドバイスに従わなかった俺に腹を立てていた。
俺が何も言い返さないと飯田は、また続けた。「俺にとっては、プロになれるかもしれないチャンスだったんだ。あの人の言うとおり曲を直すと約束してたら…俺達は、なんのために練習してきたんだよ。少しでも多くの人に聞いて貰うためじゃないの?一度あんな風に断ったら、もう二度と誘いなんか無いよ。レコードは、もう絶対無理だ。」
俺も広兼も、なにも言わなかった。広兼も多分飯田と同じ気持ちなのだろうが、俺に遠慮している様子だった。
「もう、これ以上、このバンド続けても意味無いね。」そう言うとやっと飯田は、車を走らせた。
通り過ぎてゆく街のネオンを眺めながら、俺は、自分が今井ディレクターに言った言葉を思い出していた。
「せっかくですけど、今は、自分の書いた曲をすこしでもいじる気には、なれません。どのフレーズもメロディも、今の自分そのものなんです。今のところ、俺は、自分のために歌ってるんです。人に理解して貰うより、とにかく吐き出したいんです。だから……。」
そこまで話すと、今井ディレクターの笑顔が消えるのがわかった。今井ディレクターは、大人らしく、にが笑いしながら、こう言った。「まあ、また気が変わったら、コンテスト受けに来なさい。悪いようには、しないから。」
俺は、街はずれで車を降りた。正直いって後悔もあった。飯田の言うことも解らないでは、なかった。どうして、あれほどまでに、こだわりを持ってしまったのか、自分でも不思議な気がした。俺は、あれこれと考えながら、うろついて見ず知らずの赤ちょうちんに潜り込んだ。冷や酒をあおった。これ以上考えるのが、億劫になった。たて続けに四杯流し込んだ。透間風の吹き込むこの店でも、飲んだら寒さを忘れることができた。
酔いたかった。目が回って立っていられないほど、酔いたかった。たいした目的も持たず大学にはいり、脳味噌が腐るほど隙をもてあまし、それでもブラブラとして、日時が解らなくなるほど眠り続ける生活に、俺は、どうしようもない絶望感を抱いていた。大切なことがなんなのか、なんのために生きているのか、コントロールできない自分の生き方が、恐ろしかった。
そんないいかげんな生活の中で、歌っている時だけが、自分を自分として確信できる唯一の時間である気がしていた。酔いがまわってきた。前を見ていることすら辛くなって俺は、やっと立って店を出た。
シトシトと雨が音もなく降っていた。ギターケースだけは、濡らしたくなくて、皮ジャンを脱ぎケースをくるんで歩いた。よろよろと五分ほど歩くのだけど地面が揺れて方角すら分からない。年の瀬を急ぐ通行人達は、明らかに俺を避け、足早に通り過ぎていく。犬まで俺を吠えた。俺は、濡れた地面に座り込んでしまいたい衝動を振りはらい立ったまま、雨をあびて息をついた。
電話ボックスが見えた。やっとの思いで電話ボックスの中へはいり、ダイヤルした。長い呼び出し音に、切ろうとした途端、聞き慣れた声が受話器の向こうから飛びこんできた。
「……。」「ごめん俺だ。酔ってるんだ。悪かったよ。こんなに遅く電話して。」
「……。」「だから、謝ってるじゃないか。むしゃくしゃして飲んだんだ。それで、右も左もわからなくなって……。」
「……。」「とにかく、迎えに来て欲しいんだ。ここは、えーと、天神から幹線沿いに来たとこ。黄色の電話ボックスから掛けているんだ。こっちに走ってくると、わかる筈さ。」
「……。」「この前は、追い返して悪かったよ。もう一度、やり直したいんだ。」
俺は、照美と話して少し落ちついて来た。俺は、よっぽど酔っていたらしく、ボックスの外にギターケースを置いたままだった。「あ、もう切るよ。とにかくここで待ってるから。」
雨は、止もうとしなかった。ギターケースを持ってもう一度電話ボックスに入ると俺は、壁に全身を預けた。遠くから、何台もの車のヘッドライトが交差して見え、やがて、目映く俺を照らし、そして通り過ぎた。俺は、雨に濡れたギターケースをバンダナでぬぐいながら、照美の車を待っていた。俺の1976年は、やがて終わろうとしていた。
終わり
最後まで完読ご苦労様でした。よかったら感想や苦情をメールしてくれたら嬉しい限りです。TOMMY
■TOMMYへお便りを出そう! 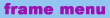
|